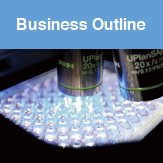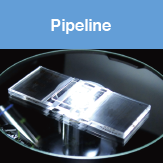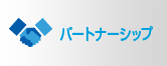- 第130回(6月26日)『先駆け総合評価相談の近況と欧州臨床腫瘍学会での発表内容』
-
株主の皆様
蒸し暑い日々が続いていますが,いまオンコリスはもっと熱い情熱をもってテロメライシンの承認申請に向けた「ラストスパート」をかけています。
既にお知らせの通り,先駆け総合評価への資料提出は,信頼性調査に関するもの以外はすべて提出を完了し,PMDAからの問い合わせ事項に対して日々対応しています。
さて,前回のブログで書ききれなかった,PMDAのテロメライシンに対する姿勢の変化について書きたいと思います。これは我々にとっても予想が難しいものでした。
まず昨年1年間,PMDAはテロメライシンの臨床評価に対して非常に厳しい姿勢で臨んできました。その裏には,昨年相次いで先駆け指定を受けた再生医療等製品2品目(A社の遺伝子治療薬とT社の細胞治療薬)が相次いで市販後臨床調査でその有効性が再現されず,承認取り下げや取り消しになったという事例がありました。さらに,S社の細胞治療薬が承認されたにもかかわらず販売が許可されなかった事例も出てきました。これはPMDAにとって,先駆け指定およびその条件付き承認が,結果として正しかったのかどうかが問われることになってしまいました。
この状況下で,PMDAはテロメライシンにも,「Phase 2の成績は確実なものであるのか?あるいは,市販後にその成績が再現されるかどうか?」に対して非常に厳しい見方をしてきました。そのためにPMDAは,テロメライシンのこれまでの資料評価よりも,市販後の全例調査ではなく,「市販後臨床試験の試験計画」を先に評価するという,承認申請前の段階としては異例の姿勢を示してきました。
この状況に対応するために,当社はテロメライシンの臨床試験研究会の医師にも同席頂いてPMDAとの面談を行い,『食道がん局所治療の世界でテロメライシンはほかに例のない医薬品となりうること,手術も抗がん剤治療もできない高齢者を中心とした患者に対して放射線療法と併用できる唯一の救いになれること』,などを主張して頂き,ようやくPMDAも評価を前向きに進めようという姿勢になってきました。
更に,非常に重要な情報が国立がん研究センターから報告されてきました。それは,「テロメライシンのPhase 2を実施した施設で,過去10年にさかのぼって,食道がんに放射線治療だけを行った症例のデータを集めて,実際にその有効性を内視鏡で判定した結果は,『治療開始6か月で22%が局所完全治癒(L-CR)であった』」というものです。このような食道がんに放射線治療だけを行った局所奏効率の臨床データは、これまで世界の何処からも報告がありませんでした。この結果は,来月スペインのバルセロナで行われる欧州臨床腫瘍学会で発表される予定になっています。
皆様にはすでにご報告の通り,当社が実施した日本での多施設臨床試験(Phase 2)ではL-CR率が41.7%という成績が得られており,この結果によってテロメライシンは食道がんに対して十分な効果を示したことが統計学的にも強く示唆されるに至ったわけです。
このような経緯を経て,PMDAはテロメライシンの臨床効果に対してポジティブな印象を持つに至り,臨床評価はすでに峠を越え,現在承認申請に向けて非臨床,品質などを含めた詳細な評価検討を行っています。
当社はPMDAとの対話を積極的に進め,年内の承認申請を達成するために最大の努力を行い,全社員がラストスパートをかけています。そして,テロメライシンが食道がん治療の新たな選択肢になり,患者様や医療現場に大きく貢献できるよう全力を尽くして参ります。
2025年6月26日
オンコリスバイオファーマ株式会社
代表取締役社長 浦田泰生
社長コラム
社長コラム 2025
- 第129回(5月26日)『先駆け総合評価相談の見通しについて』
-
株主の皆様
いよいよ梅雨の季節が近づいてきました。製薬業界ではトランプ大統領の医薬品への関税や薬価への干渉が問題となり,混沌な状況が続いています。我々バイオ業界への影響も未知数です。
皆様にお世話になりました株主総会からはや2か月がたちました。その間にもテロメライシンを取り巻く状況は日々進歩を続けています。先駆け総合評価も本格的に始まり,臨床部門は既に峠を越えており,添付文書にどのような効能効果を書くのか,どのような注意事項を記載するのかなど,PMDAとかなり具体的な内容の討議に移ってきています。更に,ご報告いたしましたように,非臨床や品質に関する資料を提出し、評価も始まりました。
ここでひとつ,皆様に訂正し説明させていただきたいことがあります。それは,去る株主総会で株主様より「3月18日に先駆け総合評価の資料を提出したということは,原則6か月の評価期間の時計はもう動き出したのか?」というご質問がございました。その席で私は「これまでのPMDAとのやりとりから考えて,まだ確定的なことは言えません」とお答えいたしました。先日,当社とPMDAの面談があり,この点を確認したところ,既に6か月の時計は動き始めていたということが確認されました。つまり,9月18日から順次,先駆け総合評価を終える予定で動き始めているということです。これは我々の認識違いであり,ご質問された株主様,および全ての株主様に訂正し説明させていただきました。したがって、テロメライシンの年内承認申請の可能性がより高まったというように認識しています。
このようにPMDAが最近になってテロメライシンの評価に非常に前向きになったのにはいくつかの理由があるようです。この点につきましては後日,またご説明させていただく機会を待ちたいと思います。
一方,当社ではそういう可能性も考えて,全ての審査資料を前倒しで作成していたため,現段階では大きな問題とはなっていませんが,今後どのような指示事項が出てくるかは定かではなく,当社としましては最大限の努力をしてPMDAからの要求に迅速に対応してゆき,年内の本申請にこぎつけたいと考えています。
Festina Lente(悠々として急げ!)という私の座右の銘がございます。今こそ,これまで築き上げてきたテロメライシンの全ての情報を冷静な目線で良く整理して,PMDAに理路整然と伝えられるよう日々努力を怠らず,そして期限厳守をして前に進んでゆきたいと考えています。
今後も皆さまのご支援とご指導を賜りますよう,よろしくお願い申し上げます。
2025年5月26日
オンコリスバイオファーマ株式会社
代表取締役社長 浦田泰生
- 第128回(1月6日)『2025年 年頭所感』
-
株主の皆様
あけましておめでとうございます。
お正月休暇もあっという間に終わったような気がします。
今年は様々な国で政権交代が行われるようで、特にアメリカでは、まもなくトランプ政権が発足しますが、今後の製薬業界にどのような波紋が広がるか、大変気になるところではあります。さて、お伝えしておりますOBP-301の承認申請ですが、昨年は誠に残念ではありましたが、PMDAとの調整に想定以上の時間を要してしまいました。当社としては何とか昨年中に直接承認申請に持ち込む方針を立てていましたが、PMDAの意向として先駆け総合評価に一旦持ち込んだ後に承認申請に進むということで合意に至りました。
承認申請後の市販後調査の方法や新製剤の品質評価など、承認に至るまでの課題はまだ残っていますが、全精力を傾けて先駆け総合評価を通過させ、可能な限り早期に承認申請に持ち込みたいと考えています。さらに、承認申請後を見据え、OBP-301の製造販売体制をさらに充実させてゆきたいと考えています。
本年も皆様のご支援を賜りますようどうぞよろしくお願い申し上げます。また、皆様のご健勝を心よりお祈り申し上げます。
2025年1月6日
オンコリスバイオファーマ株式会社
代表取締役社長 浦田泰生