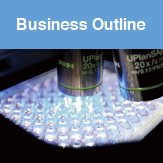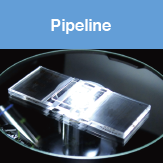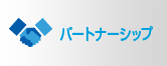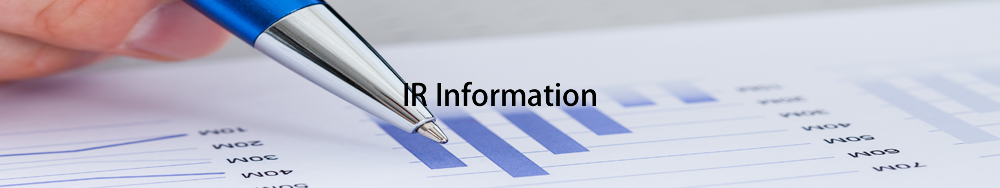よくあるご質問
 会社概要
会社概要
Q1会社の設立はいつですか?
A12004年3月18日です。創業者の浦田は、会社設立直前まで大手製薬会社で20年超、新薬開発に携わっておりました。抗HIV薬や中枢神経系、循環器系、アルツハイマー病などの薬のプロジェクトリーダーとして、その開発・上市に深く関わり、創業前には3つのがんプロジェクトを推進していました。その当時、抗がん剤開発に関してサイエンス面でのアドバイスを頂いたのが、岡山大学医学部消化器腫瘍外科の藤原先生でした。また、同時期には親族が抗がん剤の副作用に苦しみながらがんによって命を奪われるという苦い経験があり、抗がん剤開発への想いを更に強くしていました。しかし、勤務していた会社の経営判断で、がんプロジェクトからの撤退が決定しました。その後、藤原先生との再会などがあり、新たな抗がん剤の開発と商品化を目的として2004年3月に起業することを決意しました。
Q2どのような思いで起業しましたか?
A2『全く新しいコンセプトの抗がん剤を医療の現場に届けたい』と考えました。創業以前、ウイルスでがんを破壊することを研究している海外のバイオベンチャー企業を訪問した際には、「自分のやりたいプロジェクトを立ち上げて開発を進めている夢のような仕事」、「日本で同じことが出来たらよい」という想いを強く持ちました。がん学会で久し振りに岡山大学の藤原先生と再会した際、「ウイルスでがんを破壊する」という全く同じアイデアで研究を行っていることを知りました。それが現在の腫瘍溶解ウイルスOBP-301(テロメライシン)です。更に、先生は、テロメライシンを研究に留めるのではなく、事業化するための企業設立を検討していました。そのために、テロメライシンを商品化まで漕ぎ着けられるノウハウを持った経営者を探していました。浦田は、テロメライシンの特許取得の目途を確認した上で、「サイエンスと経営を分離すること」、「スリムな経営を行うこと」などを先生と約束し、代表取締役社長として起業しました。
Q3どのような事業を行っていますか?
A3「ウイルス学に立脚した創薬」というコンセプトの下、がんと重症ウイルス感染症を事業領域としています。現在、がんを対象に、「がんのウイルス療法テロメライシン(OBP-301)」、「がん抑制遺伝子p53を搭載した次世代テロメライシンOBP-702」、「ウイルスでがんを光らせる検査薬テロメスキャン(OBP-401)」の開発を行っています。また、重症ウイルス感染症領域では、「新型コロナウイルス感染症治療薬OBP-2011」の開発を行っています。
新たな対象疾患として、抗HIV薬として開発を進めていた「核酸系逆転写酵素阻害剤 OBP-601」は、ライセンスアウト先によって神経変性疾患への応用が図られています。”オンコリスなしでは医療現場が、ひいては患者様が困る”。そういう存在感のある創薬を展開することを基本方針とし、いち早く医療現場の課題解決に貢献してゆきたいと考えています。
新たな対象疾患として、抗HIV薬として開発を進めていた「核酸系逆転写酵素阻害剤 OBP-601」は、ライセンスアウト先によって神経変性疾患への応用が図られています。”オンコリスなしでは医療現場が、ひいては患者様が困る”。そういう存在感のある創薬を展開することを基本方針とし、いち早く医療現場の課題解決に貢献してゆきたいと考えています。
Q4なぜ、「希少疾病」に取り組みたいと思ったのですか?
A4世界には有効な治療がなく、救われない病気で苦しんでいる患者様が多くいらっしゃるためです。医療現場には、手の施しようがない難病に対して、地道な研究を続けている医師がたくさんいらっしゃいます。しかし、医師の力だけでは難病治療薬を世に出すことは不可能です。当社には、創薬開発で培った経験・知識、希少疾病に造詣の深い医師やバイオベンチャー企業とのネットワークがあります。また、世界では使われていても、患者数が少ないという理由で日本では未承認の薬を導入し、いち早く患者様の元に届けるという夢を実現するため、希少疾病治療薬に関するパートナーシップも広く募集しております。
Q5社名の由来は何ですか?
A5創業時の想いを社名に込めました。
「オンコリス」
テロメライシンは、腫瘍溶解ウイルス(oncolytic virus)です。オンコリスは、がんを破壊する(oncolysis)という意味の医学用語を基にした造語で、「がんをやっつける薬を新たに作る」という想いを込めました。
「バイオ」
テロメライシンは遺伝子改変ウイルスであり、バイオ創薬の1つです。「バイオ創薬を次世代医療に活かしたい」という想いを込めました。
「ファーマ」
医薬品を示すpharmaceuticalsの略語です。「薬の開発に携わり、商品化して医療現場に届ける」という想いを込めました。
「オンコリス」
テロメライシンは、腫瘍溶解ウイルス(oncolytic virus)です。オンコリスは、がんを破壊する(oncolysis)という意味の医学用語を基にした造語で、「がんをやっつける薬を新たに作る」という想いを込めました。
「バイオ」
テロメライシンは遺伝子改変ウイルスであり、バイオ創薬の1つです。「バイオ創薬を次世代医療に活かしたい」という想いを込めました。
「ファーマ」
医薬品を示すpharmaceuticalsの略語です。「薬の開発に携わり、商品化して医療現場に届ける」という想いを込めました。
Q6どのような組織で運営されているのですか?
A6当社の組織に対する考えは「縦割り組織ではなく、課題解決に対して有機的に対応できるプロジェクトチームの複合体のようにしたい」というものです。しかしながら、現在では当社はまだまだ発展途上であり、理想とする組織像にはまだ至っていない、と考えています。企業発展の要は人材育成です。今後は若い社員を採用し、五感で研究開発に触れることで、入社2-3年後にはプロジェクトリーダーに抜擢することが出来る創薬企業を目指しています。現在の採用情報についてはこちらをご覧ください。また、ビジネス面では、医薬品の開発・製造・販売権を付与することで対価を得るライセンス型事業モデルを中心に事業を進めています。また、臨床試験の進捗状況などを勘案した上で、自社で製造販売承認を得る製薬会社型事業モデルも検討します。
 経営戦略
経営戦略
Q1どのような事業活動により収入を得る事業モデルですか?
A1ライセンス収入モデルの創薬型と自社で製造販売を行う製薬会社型のハイブリッド経営で事業を展開しています。
一般に新薬の開発には10~15年、数百億円以上のコストがかかると言われています。そのため、新薬を短期間で開発して販売することは出来ません。当社は医薬品の開発を一定段階まで進め、残りの開発・販売を製薬会社に任せ、その対価として、契約に基づき開発の進展に応じたマイルストーン収入と市販後の売上高に応じたロイヤリティ収入を受け取ります。創業以来、この創薬型ライセンス収入モデルを中心に事業を展開してきました。
一方で、テロメライシンの放射線を併用した食道がん臨床試験は国内の承認申請を目指しており、医薬品として販売するステージに近づいています。当社は、テロメライシンの国内での販売パートナーの獲得に向けた活動と並行して、自社での製造販売体制の構築を進めています。
各プロジェクトのステージに応じて、ライセンス型と製薬型を機動的に選択するハイブリッド経営により、安定した収入基盤の構築を目指しています。
一般に新薬の開発には10~15年、数百億円以上のコストがかかると言われています。そのため、新薬を短期間で開発して販売することは出来ません。当社は医薬品の開発を一定段階まで進め、残りの開発・販売を製薬会社に任せ、その対価として、契約に基づき開発の進展に応じたマイルストーン収入と市販後の売上高に応じたロイヤリティ収入を受け取ります。創業以来、この創薬型ライセンス収入モデルを中心に事業を展開してきました。
一方で、テロメライシンの放射線を併用した食道がん臨床試験は国内の承認申請を目指しており、医薬品として販売するステージに近づいています。当社は、テロメライシンの国内での販売パートナーの獲得に向けた活動と並行して、自社での製造販売体制の構築を進めています。
各プロジェクトのステージに応じて、ライセンス型と製薬型を機動的に選択するハイブリッド経営により、安定した収入基盤の構築を目指しています。
Q2他の創薬バイオベンチャー企業との違いはありますか?
A2当社はウイルスの増殖能力を利用してがんを殺す「がんのウイルス療法」と、ウイルスの増殖を止める「重症ウイルス感染症治療薬」を事業領域とし、ウイルスを軸にした業界でも類を見ない『ウイルス創薬』を展開しています。
「Proof of Concept(POC)の確認に時間を要するがん領域」と、「相対的に短期間でPOCを確認出来る重症感染症」の2つの異なる時間軸を組み合わせることで、事業の安定化を図っています。
「Proof of Concept(POC)の確認に時間を要するがん領域」と、「相対的に短期間でPOCを確認出来る重症感染症」の2つの異なる時間軸を組み合わせることで、事業の安定化を図っています。
Q3どのような想いで創薬事業に臨んでいますか?
A3世界には良い薬がまだまだ少ないと強く思っています。当社は、4つの条件を満たした薬を良い薬と考えています。それは、「よく効く」、「副作用が少ない」、「摂取しやすい」、「医療関係者が困っていることを解決する」の4点です。まだ救われない患者様は多くいらっしゃいます。医療現場は、新たな薬を待ち望んでいます。
命は与えられたが、薬が無い。このような患者様を少しでも早く救うために、今後も一貫して創薬開発を進めていきます。「オンコリスなしでは医療現場が、ひいては患者様が困る」そういう存在感のある創薬を展開していきたいと考えています。社長メッセージもあわせてご覧ください。
命は与えられたが、薬が無い。このような患者様を少しでも早く救うために、今後も一貫して創薬開発を進めていきます。「オンコリスなしでは医療現場が、ひいては患者様が困る」そういう存在感のある創薬を展開していきたいと考えています。社長メッセージもあわせてご覧ください。
Q4パイプラインの最新の開発状況はどこで入手できますか?
A4最新の決算短信の末尾をご確認ください。当社パイプラインの開発状況を記載しています。決算短信には、IR情報の決算短信のページからアクセスください。
 パイプライン
パイプライン
■がんのウイルス療法テロメライシン OBP-301(suratadenoturev)
Q1開発のきっかけを教えてください。
A1『全く新しいコンセプトの抗がん剤を医療の現場に届けたい』と考えました。
創業者であり代表取締役社長である浦田が、当社の創業を考える以前、尊敬する親類を相次いでがんで亡くしました。その病室での姿は、がんで苦しんでいるのか、抗がん剤の副作用で苦しんでいるのか、分からないほど憔悴しきっていました。製薬企業に勤務している私には、何も手助けできないという忸怩たる思いが心に残りました。その後、「ウイルスでがんを破壊する」ことを研究している海外のバイオベンチャー企業がアメリカやカナダでいくつもあることを知り、その初期の臨床成績では、ほとんど副作用らしいものがないことを知り、大変驚きました。このような医薬品開発を日本でも立ち上げてみたいという想いを強く持ちました。丁度その頃、日本がん学会で久し振りに以前よりお世話になっていた岡山大学第1外科の藤原先生と再会し、「ウイルスでがんを破壊する」という全く同じアイデアで研究を行っていることを知りました。それが現在のがんのウイルス療法テロメライシン(OBP-301)です。そして先生とともに何か月も研究開発方針や特許の確実性に関して議論を繰り返し、その結果、2004年3月にテロメライシンを事業化するために起業しました。
創業者であり代表取締役社長である浦田が、当社の創業を考える以前、尊敬する親類を相次いでがんで亡くしました。その病室での姿は、がんで苦しんでいるのか、抗がん剤の副作用で苦しんでいるのか、分からないほど憔悴しきっていました。製薬企業に勤務している私には、何も手助けできないという忸怩たる思いが心に残りました。その後、「ウイルスでがんを破壊する」ことを研究している海外のバイオベンチャー企業がアメリカやカナダでいくつもあることを知り、その初期の臨床成績では、ほとんど副作用らしいものがないことを知り、大変驚きました。このような医薬品開発を日本でも立ち上げてみたいという想いを強く持ちました。丁度その頃、日本がん学会で久し振りに以前よりお世話になっていた岡山大学第1外科の藤原先生と再会し、「ウイルスでがんを破壊する」という全く同じアイデアで研究を行っていることを知りました。それが現在のがんのウイルス療法テロメライシン(OBP-301)です。そして先生とともに何か月も研究開発方針や特許の確実性に関して議論を繰り返し、その結果、2004年3月にテロメライシンを事業化するために起業しました。
Q2どのような特徴がありますか。
A2「風邪のウイルスでがんを破壊する薬」を目指し、開発しています。がんのウイルス療法テロメライシンは、正常細胞では増殖せず、がん細胞で増殖してがん細胞を破壊するように風邪のウイルスを遺伝子改変した抗がん剤です。風邪のウイルスを起源としているため、発熱程度の副作用が確認されていますが、既存の抗がん剤よりは比較的軽微な副作用となっています。現在、当社では、テロメライシンをウイルスが持つ増殖能力と免疫活性を活かした局所・全身療法として活用する可能性を探るべく、国内外で研究開発を進めています。
Q3知的財産権についてどのように考えていますか?
A3テロメライシンの特許が切れていても、オーファンドラッグ指定が成されていれば、国内では再審査期間が10年間付与されることになり、独占販売が可能となります。また、米国では上市後7年間の先発権が認められます。この間に、最終製剤を特許性のある凍結乾燥品などに変えることによって特許期間を更に延長することができると考えています。一方、バイオシミラー(BS)の問題ですが、テロメライシンのマスターウイルスバンクとその製造に用いるマスターセルバンクは当社独自のものであり、他社による作成は現行の技術では容易なものではありません。更に、製造技術も構築困難であり、仮に模倣できたとしても、最終品質で同等性を取り、安全性や有効性の同等性を証明することも容易ではないと考えます。
当社は、テロメライシンの優先期間と最終製剤特許による独占期間を最大限に活用して、独占販売を行っていきたいと考えています。
当社は、テロメライシンの優先期間と最終製剤特許による独占期間を最大限に活用して、独占販売を行っていきたいと考えています。
■核酸系逆転写酵素阻害剤 OBP-601
Q1開発のいきさつを教えてください。
A1OBP-601は、抗エイズ薬として2006年にアメリカのエール大学から導入した化合物で、鹿児島大学ヒトレトロウイルス学共同研究センター馬場雅範教授も特許権者の一人でした。自社でアメリカのFDAに治験届を出し、2009年にはフランスでPhase2a試験を行い、投与10日間で患者様の血液中エイズウイルス(HIV)の量を100分の一以下に低下させることを確認しました。2010年にはアメリカ大手企業ブリストルマイヤーズ・スクイブ製薬にライセンスされ、同社の全額費用負担でPhase2が実施されてよい結果が得られましたが、残念ながら臨床試験の最終段階Phase3の直前でライセンス打ち切りとなってしまいました。
その後、新たなライセンス先を探索してきましたが、すでにエイズ治療薬の国際的なマーケットは飽和状態に達しており、なかなかライセンス先が見つかりませんでした。しかし、2019年に、アメリカのブラウン大学の研究により、C9-ALSやアルツハイマー病など各種神経変性疾患の原因の一つが、ヒトのDNAを構成するゲノムが、細胞の中で逆転写酵素によって過剰に転写されることが分かってきました。その研究の中でOBP-601が非常に強くその反応を止め、また脳内への移行が優れているということが確認されたため、2020年6月にアメリカのTransposon社とライセンス契約を締結しました。現在、同社の全額費用負担により、新たな適応であるPSP(進行性核上性麻痺)、C9-ALS(筋萎縮性側索硬化症)やFTD(前頭側頭型認知症)などの神経変性疾患を対象に開発が進んでいます。
その後、新たなライセンス先を探索してきましたが、すでにエイズ治療薬の国際的なマーケットは飽和状態に達しており、なかなかライセンス先が見つかりませんでした。しかし、2019年に、アメリカのブラウン大学の研究により、C9-ALSやアルツハイマー病など各種神経変性疾患の原因の一つが、ヒトのDNAを構成するゲノムが、細胞の中で逆転写酵素によって過剰に転写されることが分かってきました。その研究の中でOBP-601が非常に強くその反応を止め、また脳内への移行が優れているということが確認されたため、2020年6月にアメリカのTransposon社とライセンス契約を締結しました。現在、同社の全額費用負担により、新たな適応であるPSP(進行性核上性麻痺)、C9-ALS(筋萎縮性側索硬化症)やFTD(前頭側頭型認知症)などの神経変性疾患を対象に開発が進んでいます。
Q2どのような特徴がありますか。
A2RNAの逆転写を抑制し、神経変性疾患への応用が期待される核酸系逆転写酵素阻害剤(NRTI)です。
RNAからDNAに逆転写する過程で、変異したDNAや本来と異なる場所にDNAが組み込まれる可能性があります。この減少により神経細胞が傷つけられることが、神経変性疾患の要因と考えられています。OBP-601はRNAからDNAに逆転写することを抑制することによって、これまでにない神経変性疾患の治療薬になることが期待されています。
RNAからDNAに逆転写する過程で、変異したDNAや本来と異なる場所にDNAが組み込まれる可能性があります。この減少により神経細胞が傷つけられることが、神経変性疾患の要因と考えられています。OBP-601はRNAからDNAに逆転写することを抑制することによって、これまでにない神経変性疾患の治療薬になることが期待されています。
Q3トランスポゾン社と契約に至った経緯を教えてください。
A3米国ブラウン大学の発明をもとに神経難病を対象として研究開発を進めています。この発明にOBP-601が最もふさわしい化合物としてヒットしたことがきっかけとなり、トランスポゾン社とのライセンス契約締結に至りました。
Q4ライセンス契約の内容を教えてください。
A42020年6月にトランスポゾン社との間で、主に神経領域の開発に対して全世界における再許諾権付き独占的ライセンス契約を締結しました。契約一時金及びマイルストーン収入の合計額は、総額で3億米国ドル以上です。また、総額3億米国ドルに加えて、当社は上市後の売上高に応じたロイヤリティ収入を別途受領します。さらに、トランスポゾン社がOBP-601を第三者の製薬会社等へサブライセンスした場合、当社はトランスポゾン社からサブライセンス収入の一定割合を受領します。
Q5トランスポゾン社について教えてください。
A5トランスポゾン社は、ベンチャーキャピタルの出資の下、主に神経領域を対象とした新薬開発を目的に、2019年12月にOBP-601を開発するために設立されたベンチャー企業です。トランスポゾン社は、当社からOBP-601のライセンスを導入し、ブラウン大学から用途特許のライセンスを導入しています。
CEOであるEckard Weber氏は、米国でも有名なドメイン社というベンチャーキャピタル出身で、大手製薬企業への数多くのM&Aの実績を持っています。
CEOであるEckard Weber氏は、米国でも有名なドメイン社というベンチャーキャピタル出身で、大手製薬企業への数多くのM&Aの実績を持っています。
■新型コロナウイルス感染症治療薬 OBP-2011
Q1開発のいきさつを教えてください。
A1当社はこれまでに、鹿児島大学ヒトレトロウイルス学共同研究センター馬場雅範教授と共同研究契約を締結し、エイズウイルス(HIV)、C型肝炎ウイルス(HCV)、B型肝炎ウイルス(HBV)に対する抗ウイルス薬創製に関する創薬研究を進めてきました。その結果、これまでの研究に用いてきた化合物の中に、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の原因ウイルスであるSARS-CoV-2に対して特異的で、かつ強い増殖抑制効果を有するOBP-2011を見出しました。
Q2特徴を教えてください。
A2OBP-2011はこれまでの開発において、新規メカニズムであるヌクレオカプシドの形成を阻害することを示唆する試験結果を得ています。カプシドとRNAの結合においては、さまざまな細胞内タンパクが関与しており、国立感染症研究所とともに細胞内タンパクとの影響も含めた上で、メカニズムを解明していきます。
また、これまでに行われた前臨床試験の結果から、探索的毒性試験や探索的遺伝毒性試験においても検査の異常は認められませんでした。オミクロンなどの変異型コロナウイルス株や、重症急性呼吸器症候群(SARS)および中東型呼吸器症候群(MERS)ウイルスに対しても、野生型と同等の活性を示すことが細胞培養系の実験で示唆されています。
また、これまでに行われた前臨床試験の結果から、探索的毒性試験や探索的遺伝毒性試験においても検査の異常は認められませんでした。オミクロンなどの変異型コロナウイルス株や、重症急性呼吸器症候群(SARS)および中東型呼吸器症候群(MERS)ウイルスに対しても、野生型と同等の活性を示すことが細胞培養系の実験で示唆されています。
■次世代テロメライシン OBP-702
Q1開発のいきさつを教えてください。
A1岡山大学消化器腫瘍外科の藤原教授は、1990年代にアメリカテキサス州のテキサス大学MDアンダーソンがん研究センターに留学し、『がん抑制遺伝子p53』研究の第一人者、Jack Roth教授に師事し、非増殖型のアデノウイルスベクターを用いたp53のがん遺伝子治療(ADVEXIN)を発明し、特許を出してきました。その後、藤原先生は帰国し、ADVEXINによる日本で初めてのがん遺伝子治療Phase1臨床試験を行いました。その結果、一部の症例で確実な臨床効果が認められたものの、増殖しないウイルスベクターを用いた遺伝子治療ではその効果は限定的であることが判明しました。その後、増殖するウイルスベクターを用いたテロメライシンの開発に集中することになり、放射線との併用による臨床試験では、食道がん局所に対する効果が明らかになり、中外製薬へのライセンスに成功しました。
藤原教授の最終的な目標は、世界でも最も優れた強力な腫瘍溶解ウイルスを創製することであり、先に述べましたp53の遺伝子治療ADVEXINとテロメライシンとのハイブリッドである次世代テロメライシンOBP-702が創製され、現在その開発が進められています。
藤原教授の最終的な目標は、世界でも最も優れた強力な腫瘍溶解ウイルスを創製することであり、先に述べましたp53の遺伝子治療ADVEXINとテロメライシンとのハイブリッドである次世代テロメライシンOBP-702が創製され、現在その開発が進められています。
Q2どのような特徴がありますか。
A2がんのウイルス療法テロメライシンに、がん抑制遺伝子p53を搭載した次世代テロメライシンです。p53遺伝子変異・欠損が認められるがん患者様に対してOBP-702を投与することで、テロメライシンの特徴であるテロメラーゼ陽性のがん細胞において特異的に増殖して破壊し、同時にがん細胞の中で発現されたp53蛋白質ががん細胞を自然死(アポトーシス)させる機能を有しています。
■がん検査薬テロメスキャン OBP-401
Q1どのような特徴がありますか?
A1「血中に漏れだした微量ながん細胞をキャッチする検査薬」を目指しています。既存の検査方法では、微小ながんは見つかりません。当社が開発中の血中浮遊がん細胞(Circulating Tumor Cell: CTC)検査薬テロメスキャン®(OBP-401)は、それらを見つけることが出来る可能性があります。がんの検査薬全体に言えることですが、ひとつの検査薬単体でがんを確定診断する訳ではありません。当社では、テロメスキャンをがん細胞発見の端緒となる存在、精密さを高める役割に育てていきたいと考えています。当社は、いずれがん治療には「がんの遺伝子変異を分析して適切な治療法を選択する時代が来る」と考えています。しかし、術後にがんが脳や施術部位近辺へ転移した場合、遺伝子解析のためにがん細胞を患部から直接取ることが出来ません。当社では、テロメスキャンを用いて血中を浮遊するがん細胞を捕捉し、適切な治療法選択の時代に貢献したいと考えています。テロメスキャンについては、こちらもあわせてご覧ください。
Q2リキッドバイオプシーとは何ですか?テロメスキャンとどのような関係があるのですか?
A2従来、がんの確定診断や予後判定等には、針や内視鏡を使って採取した腫瘍組織を顕微鏡で観察する病理組織学的検査法(生検:biopsy)が行われます。これに代わる検査法として近年注目されてきているのが、リキッドバイオプシー(liquid biopsy)と呼ばれる、血液等の体液サンプルから診断や治療効果予測を行う技術です。当社では、テロメスキャンのリキッドバイオプシーとしての可能性を開拓すべく、開発を進めています。
■HDAC阻害剤 OBP-801
Q1どのような特徴がありますか?
A1「遺伝子構造の変化に注目した抗がん剤」として、開発しています。2013年、米国の女優が発がん予防のために乳房を切除し、話題を呼びました。彼女の生まれ持った遺伝子配列が、高いがん発症リスクの原因だったのです。一方で、誕生時に発がん遺伝子を持たない方も、周辺環境の様々な影響によって遺伝子構造が変化し、遺伝子発現に影響を受ける場合があります。このような誕生後の後天的な遺伝子構造の変化を「エピジェネティック」な変化といいます。エピジェネティックな変化を招く酵素の1つに、ヒストン脱アセチル化酵素(HDAC)があります。がん細胞ではHDACの発現が上昇していると言われており、これにより「がん抑制遺伝子」の発現が抑制されていることが知られています。「がん抑制遺伝子」の発現が抑制されると、がん化した細胞は死滅することなく、増殖を繰り返してやがてがん組織を形成します。長野県の土壌から発見された緑膿菌が作り出す物質であるOBP-801は、HDACを阻害することで、エピジェネティックな変化を正常に戻します。その結果、がん抑制遺伝子の発現が誘導され、がん化した細胞を細胞死へ導くことでがんの増殖を抑制します。OBP-801については、こちらもあわせてご覧ください。
■その他
Q1各種パイプラインの治験に、どうすれば参加できますか?
A1大変申し訳ございませんが、当社から医療機関へご参加を斡旋することは出来ません。治験では、実際に治験に参加される方の人権と安全性を最大限守るために、病状・病歴・合併症有無・通院可否・性別・年齢などの厳密な基準が設定されています。そのため、御本人が参加を希望されても、参加頂けない場合もございます。
かかりつけの主治医とよくご相談ください。
かかりつけの主治医とよくご相談ください。
 決算関連
決算関連
Q1決算期はいつですか?また、決算発表はいつごろ行われますか?
A112月決算です。通期決算発表は毎年2月に行います。詳細はIRカレンダーをご確認ください。
Q2過去の業績推移および決算資料の確認方法を教えてください。
Q3説明会の動画配信の確認方法を教えてください。
A3アナリスト向け説明会や、株主総会後に開催しております事業説明会の動画配信を行っております。当社HPで公開している動画ライブラリをご覧ください。
Q4サイレント期間を教えてください。
A4当社は製薬会社と異なり、安定的な売上計上が無い研究開発型の創薬ベンチャー企業です。そのため、決算発表を待たず、研究開発の進捗に応じて情報開示を速やかに実施しています。
決算発表と連動せず開発状況を開示させて頂くため、サイレント期間は設けておりません。
決算発表と連動せず開発状況を開示させて頂くため、サイレント期間は設けておりません。
 株式関連
株式関連
Q1上場市場、上場日、証券コードを教えてください。
A12013年12月6日に東証マザーズ市場へ上場しました。証券コードは「4588」です。
Q2上場に至った目的は?
A2より積極的に医薬品及び検査薬の研究開発を実施するための資金調達、および優秀な人財採用を進めることが目的です。
Q3単元株式数は何株ですか?
A3100株が1単元です。こちらもあわせてご覧ください。
Q4株式名簿管理人はどこですか?
A4三井住友信託銀行です。こちらもあわせてご覧ください。
Q5株式の諸手続きの窓口はどこですか?
A5住所、氏名のご変更、配当金受取方法のご指定、その他株主としての権利行使に関連するお手続きにつきましては、お取引の証券会社までお問い合わせください。但し、特別口座で株式をお持ちの株主様は、三井住友信託銀行株式会社にお問い合わせください。
Q6株主優待制度はありますか?
A6現在は、設けておりません。
Q7配当金はいつ現在の株主に支払われますか?また、いつごろ支払いされますか?
A7当社は、研究開発型ベンチャー企業として、先行投資的な事業資金等を支出してまいりましたため、これまで利益配当の実績はありません。しかしながら、株主に対する利益還元を重要な経営課題として認識しており、今後の株主に対する利益配分については、今後の経営成績及び財政状況を勘案しながら早期に配当を実現すべく、検討してまいります。
Q8これから株価はどうなるのでしょうか?いつ売る(買う)のがよいのでしょうか?
A8大変申し訳ありませんが、当社では個人の投資に関する助言や、将来に関する予測、株価に関する意見等は申し上げられません。投資に関する意思決定は、投資家様ご自身の判断でなされますようお願い申し上げます。
Q9いつIRが出ますか?
A9大変申し訳ありませんが、将来に関する予測、株価に関する意見等は申し上げられません。また、当社は、法令に基づき、開示すべき情報は適時に開示しており、他方で開示すべき状況にない未公表の情報については、お問い合わせをいただいても一切開示することができないものとなりますので、この点ご理解を賜れますと幸いです。
Q10社長コラムの更新日を教えてください。
A10定期的な更新日は設定していません。長期保有の投資家各位から頂いたご質問を参考に、当社事業説明の一環としてコラム掲載させて頂いています。
Q11公告の方法について教えてください。
A11当社HPにて電子公告で開示します。
Q12現在の株価はいくらですか?
A12株価情報につきましては「株価情報」をご確認ください。
 株主総会
株主総会
Q1株主総会はいつ開催されますか?
招集通知はいつ届きますか?
招集通知はいつ届きますか?
Q2株主総会でお土産はありますか?
A2お土産のご用意はありません。
Q3株主総会終了後に事業説明会はありますか?
A3株主総会終了後、経営陣から株主様へ事業の状況等を直接説明差し上げる時間を設けております。質疑応答の時間もございますので、多くの株主の皆様に株主総会と共にご出席を賜れますと幸いです。
また、事業説明会の模様は、終了後2週間程度で当社HPに動画を掲載させて頂きます。過去の動画に関しては、こちらをご参照ください。
また、事業説明会の模様は、終了後2週間程度で当社HPに動画を掲載させて頂きます。過去の動画に関しては、こちらをご参照ください。
Q4郵送されてきた議決権行使書を紛失してしまいましたが、株主総会に出席できますか?
A4株主総会の受付で、議決権行使書を紛失された旨をお申出ください。所定の用紙に株主名簿記載の住所・氏名等をご記入いただきます。株主さまであることのご本人確認ができましたら、株主総会会場へご入場が可能です。
 その他一般
その他一般
Q1問い合わせしたい場合はどうすればよいですか?
A1当社では、お問い合わせに対して個別に電話やメールなどで回答することは公平性の観点から控えています。HPの「お問い合わせフォーム」よりお問い合わせ頂いた内容のうち、当社をご理解頂くために有益であると判断したご質問を「よくあるご質問」として取り上げ、不定期に開示するプレスリリース形式で回答しています。そのため、お問い合わせ内容によっては、ご返答を差し上げない可能性がございます。あらかじめご了承ください。
Q2IR情報のメールマガジン登録をしましたが、その後メールマガジンを受信できません。
A2メールマガジンへご登録いただき、ありがとうございます。一度登録手続きに進まれた後の再登録は、二重登録となり登録がはじかれる場合がございます。登録状況を確認させていただくため、当社HPの「お問い合わせフォーム」よりメッセージをお送りください。。